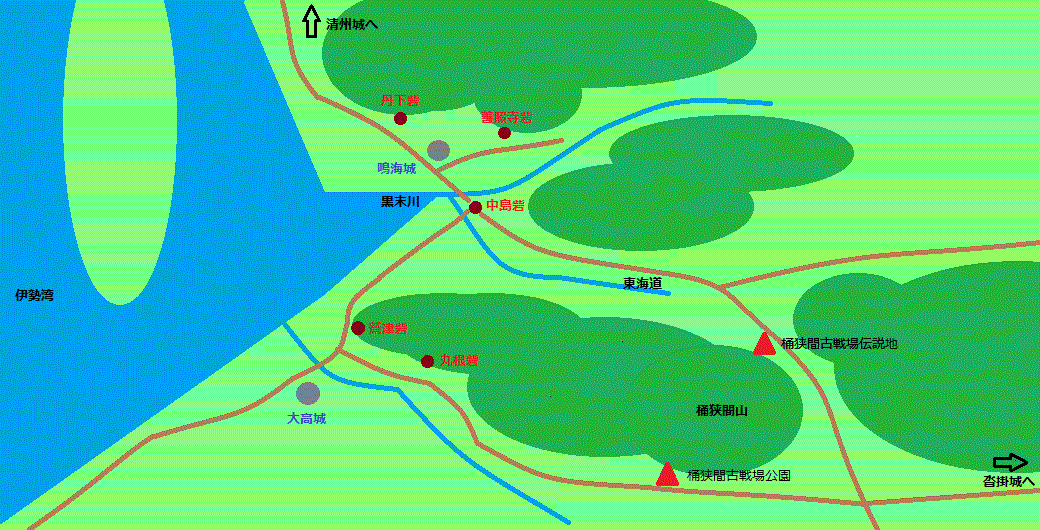| 桶狭間古戦場跡 |
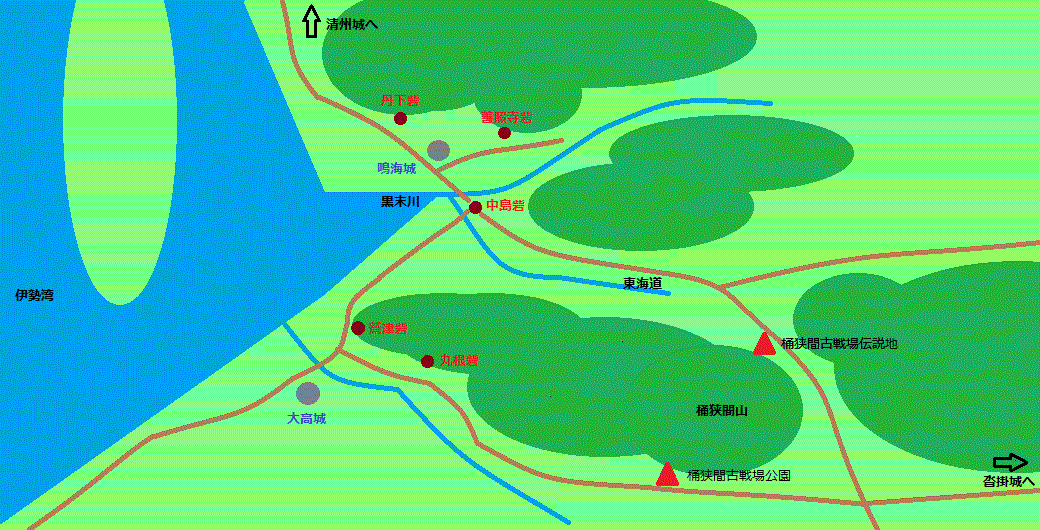 |
 |
 |
桶狭間古戦場公園
(愛知県名古屋市緑区桶狭間) |
1560年に桶狭間の戦いがあったとされる場所のひとつ。
近くに桶狭間山と呼ばれた山があり、今川義元の本陣があったとされる。
(メモ)
公園内には立派な銅像が建っている。
駐車場がないので要注意。 |
|
| 桶狭間古戦場伝説地 (愛知県豊明市栄町南館) |
1560年に桶狭間の戦いがあったとされる場所のひとつ。幾つかある候補地で唯一、国の史跡指定を受けている。
今川義元に殉じた家臣のひとり、松井宗信の子孫が建てた墓碑や義元の墓がある。道を挟んだ向かいの高徳院は義元が本陣を置いた場所とされる。
(メモ)
最寄り駅は名鉄の「中京競馬場前」。駅を挟んで北側に競馬場、南側に古戦場伝説地がある。そのため、中京競馬場のG1レース「高松宮記念」で、実況アナウンサーが「桶狭間決戦」というフレーズをよく使う。 |
 |
 |
 |
| 伝説地にたつ石碑 |
今川義元の墓 |
高徳院(今川義元本陣跡) |
|

鳴海城跡の石碑 |
鳴海城 (愛知県名古屋市緑区鳴海町城) |
| 天守:なし |
戦国期を中心とした主な歴史
応永年間(1394~1428)に築城されたといわれる。
天文年間(1532~1555)織田信秀配下・山口教継、教吉親子が城主をつとめる。
1552年 織田信秀病没。その後、山口親子が今川義元に寝返る。
1553年 山口親子、織田信長の軍勢から城を守る。
1558年頃 今川家臣・岡部元信が在番として送り込まれる。
1560年 桶狭間の戦い。岡部元信、信長に対し、今川義元の首返還を条件に開城。
(メモ)
石碑と案内板は神社となっている二の丸跡にある。道路を挟んで向かいにある公園が本丸跡。そこには土塁などわずかながら遺構が残っている。 |
|

本丸跡 |
沓掛城 (愛知県豊明市沓掛町) |
| 天守:なし |
戦国期を中心とした主な歴史
応永年間(1394~1428)に築城されたといわれる。
室町時代を通じて近藤家が城主をつとめる。
1541年頃 近藤景春、尾張・織田信秀に従う。
1551年 織田信秀病没。景春、織田家の勢力が弱まったため、今川義元に従う。
1560年 桶狭間の戦い。景春、織田家に抵抗するが討死。
同 年 簗田政綱が城主となる。
1575年 政綱、加賀へ転封。織田信照を経て川口宗勝が城主となる。
1600年 関ヶ原の戦い。宗勝、西軍につき敗北。伊達政宗の預かりとなり、廃城。
(メモ)
1560年の桶狭間の戦いで、今川義元は駿府を出陣して、まずこの城に入った。松平元康(のちの徳川家康)が大高城への兵糧入れを成功させた翌日、沓掛城から大高城へ向かう途中の桶狭間で義元は織田信長の奇襲にあい非業の死を遂げた。
城跡は公園となっているが、堀、土塁、曲輪跡など遺構がしっかりと残っている。侍屋敷跡が車を10台ほど止めれる駐車場となっているが、駐車場までの道は細く、対向車に来られると厄介。
|









 模擬天守
模擬天守